東海大学児童教育学部では、教育・保育現場、高等学校からの要望に応じ、幼児児童、高校生、教員、保護者、施設職員などを対象とした出張講義を行っております。ご希望の方は、このページの下部にある申込フォームよりお申し込みください。
<講師料>無料

名前をクリックすると講義内容の詳細にジャンプします。
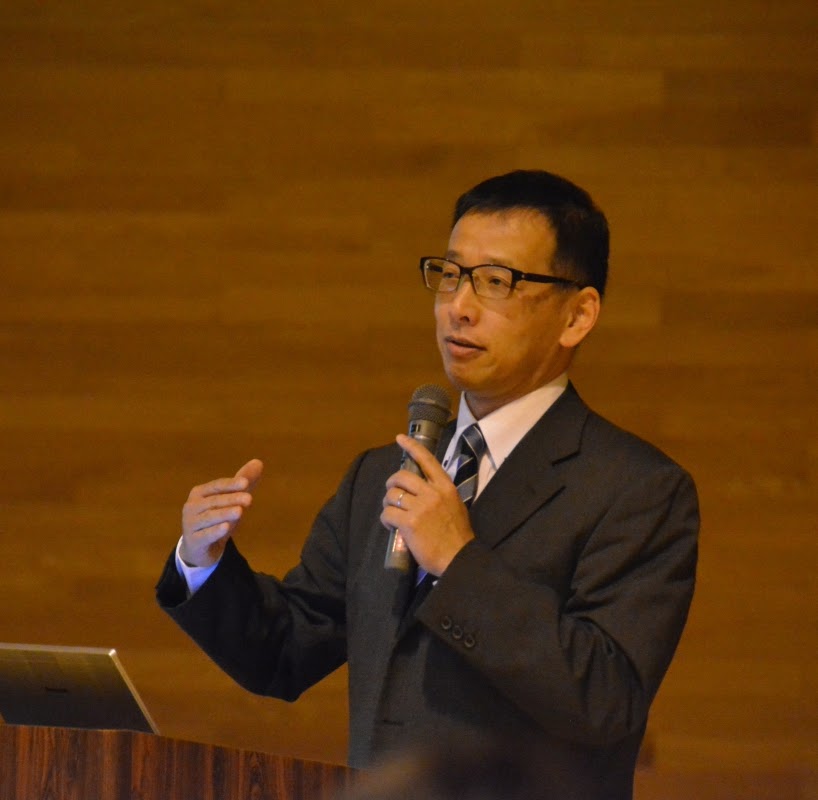
専門分野:
国語科教育、日本近代文学主な授業:初等国語、初等国語科教育法
研究テーマ:
・小学校国語教育における文学教材(特に詩歌)の在り方に関する史的研究
・学校教育の言語教育の在り方に関する研究
今、学校教育は大きな転換期に来ています。これからの時代に求められる資質・能力の形成に向けて、いかにして主体的な「学び」を成立させていくのかが問われています。そこでは思考力や感性の形成に大きく関わる「言語力」はどのように捉えるべきか。国語科のみならず、教育全般の文脈の中で、課題を考え、実践的な展望を皆さんと考えていきたいと思います。
現在、保育・教育の在り方が大きく変わってきています。これまでのような知識重視型の教育ではなく、持っている知識をもとに、主体的態度で多様な考えを持つ人々と関わることを重視する教育になってきています。このような新しい学びの姿には、不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。子育ての中で、どのように向き合えばいいのか、その点について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
言葉を習得する過程にある子どもにとっては、大人が普段当たり前のように使っている言葉「日本語」も、日々新鮮な輝きを持ったものです。言葉との出会いを通して、子どもは大きく成長していきます。詩歌や言葉遊びを通じて、子どもの言葉の世界を広げて生きたいと思います。
皆さんは、「詩」を普段から読んでいますか? あまり読んだことがないという方が多いのではないのでしょうか。しかし、J-ポップなど音楽を通して、多くの「歌詞」に触れているかと思います。現代の「歌詞」も含めて、詩歌の中には、日常生活をぱっと照らし出すような一節、感動を引き起こすフレーズがたくさんあります。それは言葉の力といっていいでしょう。言葉がどのような「力」を持っているのか、一緒に体験してみましょう。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。
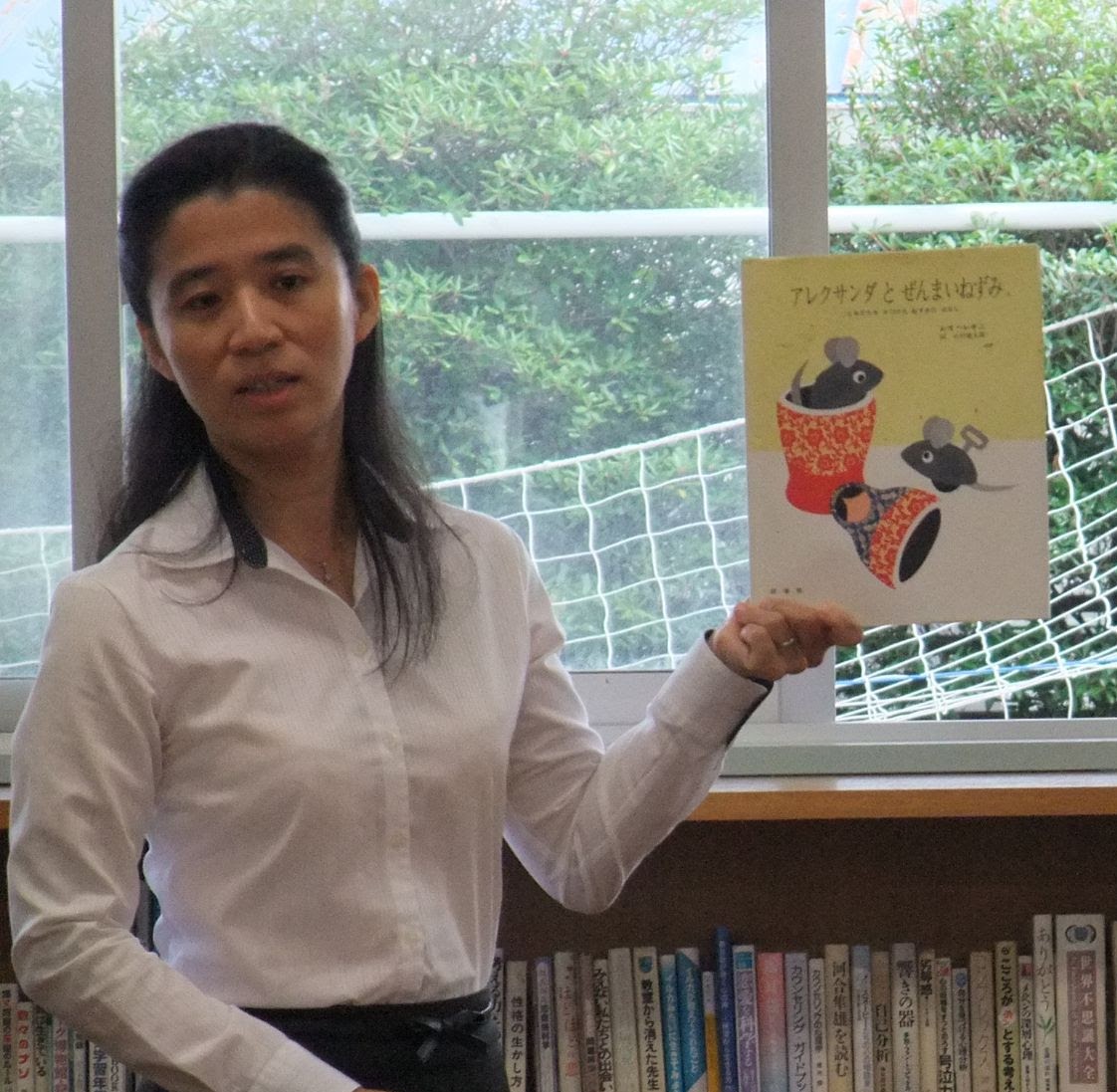
専門分野:
児童文化、児童文学、保育史
主な授業:
言葉の指導法、保育原理、子どもと文学
研究テーマ:
・児童文化財に関する研究(絵本、紙芝居など)
・日本におけるアンデルセン童話
・日本の保育の歴史と「お話」
視覚的なものを何も持たずに行う素話(ストーリーテリング)は子どもの想像性を広げます。また、絵本は「めくる」という動作によって動きがでますし、紙芝居というお芝居は、語り手と大人数の聞き手に共感性をもたらします。このように、子どもの周りにあるさまざまな「お話」には、それぞれに魅力があります。子どもを取り巻く「お話」の世界の面白さについてお話しします。
現在、子どもの周りにはたくさんの絵本があふれています。乳幼児期の子どもにとって、絵本は「誰かに読み聞かせてもらうもの」であり、必ず自分以外の他者が必要となります。だからこそ、この時期の絵本は大人と子どもの間に存在してこそ、もっともその魅力が発揮されるものと考えています。このような考えをもとに、絵本の読み聞かせ方、選び方についてもお話しします。
素話(ストーリーテリング)、絵本、紙芝居、パネルシアターなど、同じ「お話」でも、その形や表現方法が変わることで、あらたな魅力・面白さを感じることができます。このような、さまざまな児童文化財を通して、子どもにいろいろな「お話」を語ることを通して、子どもの「お話」の世界を広げたいと思います。
大人になると、子どもの頃とは絵本の見方が変わってきます。だからこそ、高校生の今、もう一度子どもの目線で絵本を見ることで、その魅力が再発見することができます。同時に、その絵本を子どもがどのように見ているのか・感じているのかという視点から捉えることは、子どもの気持ちを理解することにつながります。子どもから見た絵本の世界の面白さを、絵本の読み聞かせのコツも含めながら、お話しします。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。
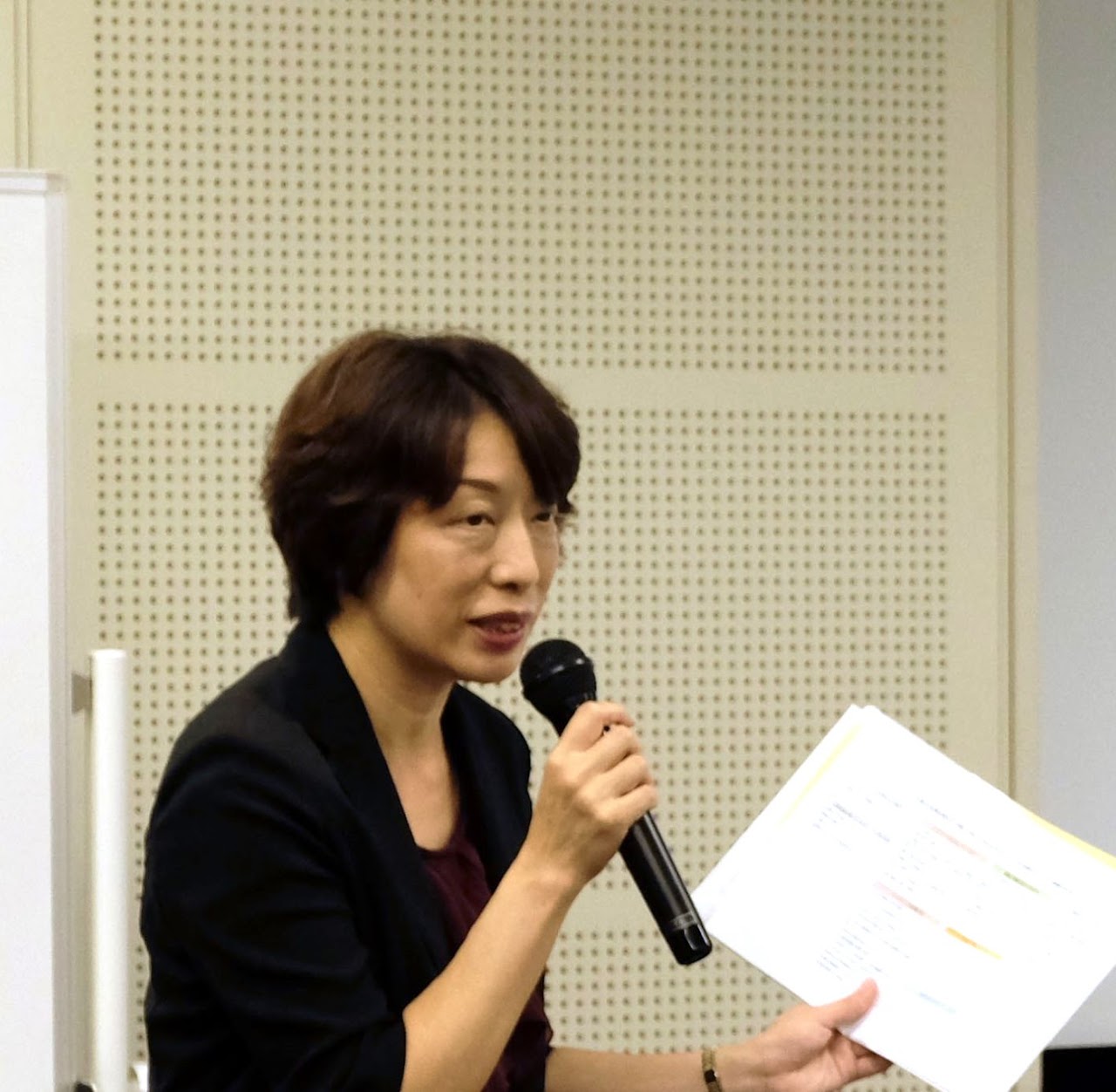
専門分野:
子ども学、保育学
主な授業:
人間関係、人間関係の指導法、実習指導(幼稚園)
研究テーマ:
・幼児と中高生とのふれ合い体験活動
・保育者のリーダーシップとミドルリーダーシップ
・保育者を育てるパターン・ランゲージ
・おとなと子どもの哲学対話
幼稚園や保育所、認定こども園等において、よりよい園をつくるためには、そこに関わる全ての教職員が、役職や経験年数という枠を越えて、互いに多様な会話・対話を積み重ねて交流し、切磋琢磨して成長し合う関係を築くことが大切です。本講義では、教職員間での対話の進め方、対話のための場づくり、ファシリテーションのやり方等について対話のワークを取り入れながら、体験的に学びます。
日々、子育てをしていると、沢山の「わからないこと」に出会うのではないでしょうか?本講義では、哲学対話という対話を取り入れて、保護者の皆さんが共に集い、「問い」を出し合い、一緒に考えを深めていきます。哲学というと難しそうに思われるかもしれませんが、哲学の知識は不要です。哲学的な問いは私たちの日常の中に沢山あることに気づいて頂けると思います。頭の中を柔らかくして、是非ご一緒に哲学対話を楽しみましょう。
さて、みなさんに質問です。あなたは大人ですか?それとも子どもですか?これは、ある保育所の4歳の女児が、職場体験で保育所に来ていた中学3年生のお兄さんに尋ねたことです。「お兄ちゃんは、大人なの?子どもなの?」。「大人」と「子ども」は何が違うのでしょうか?私たちは、どうやって「大人」と「子ども」を見分けているのでしょうか?本講義で「子ども」について一緒に学びましょう。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。
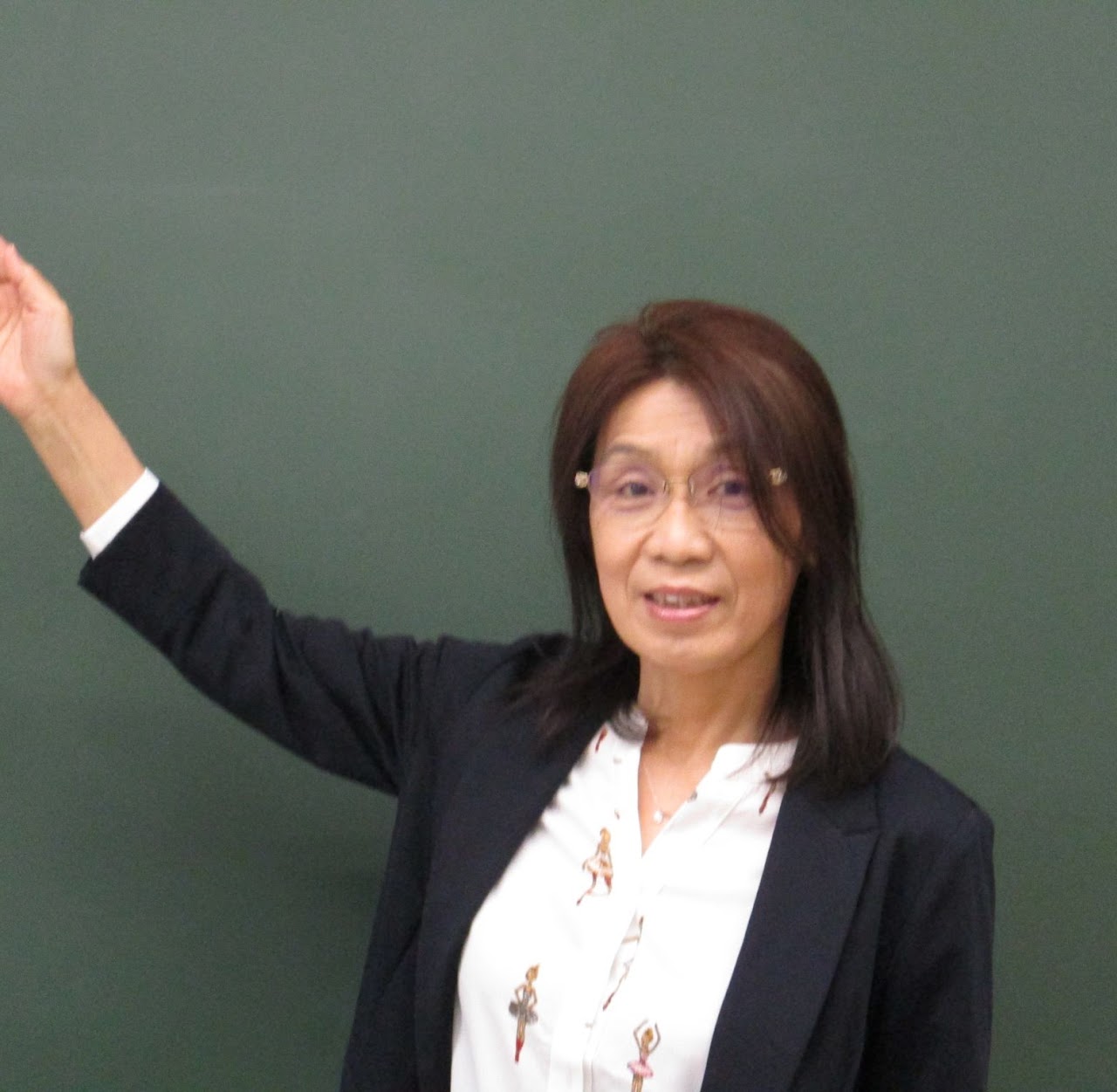
専門分野:
保育学
主な授業:乳児保育、子育て支援
研究テーマ:
・地域の多様な子育て家庭の現状から今後の子育て支援の在り方を探る
社会の変化や価値観の多様化等により、現代の子育て環境は大きく変化し、子育ての困難さを感じている子育て家庭は少なくありません。「子どもの最善の利益」を基本に、多様な子育て家庭における支援について、そして、園だけでは支えきれない子育て家庭や子どもの育ちを支えていかれるよう一緒に考えていきたいと思います。
子どもの持つ力を信じ、乳児期の望ましい未来をつくり出す力を引きだしていく大人の関わりについてお話します
あかちゃんの持つ力について、そして、子どもにとっての遊びや子どもが高校生等地域の人と関わることにどんな意味があるのかなど、エピソードを交えてお話したり,おもちゃ作り体験しながら伝えていきます。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
英語教育、異文化・国際理解、教師教育
主な授業:
EGP、ESP、外国語教育政策、英語科教育法
研究テーマ:
・一貫性英語教育
・SDGsと英語教育の融合
・英語教員の資質能力
2020年4月、小学校で英語が教科になりました。長きにわたり、小学校英語の必修化や教科化を求める声が続く一方、教育現場や保護者の不安や不満が消えることはありませんでした。たくさんの課題を抱えたまま走り出した小学校英語を軸に、「こうあるべき」英語教育の誤った通念から脱却し、校種間・教科間や産官学の連携のもと、全ての人々が関わって、子ども達の「生きる力」の育成と将来を見据える教育実践のヒントをお話しします。
なぜ、日本で外国語や英語を学ぶのでしょうか。外国語教育の役割はただ単に、目標言語のネイティブらしい発音や、読み・書き技能を身につけることではありません。一説には世界の言語数は7,000と言われています。その1つである英語を私たちが学ぶ意味・意義、また、高校生・大学生が目指すべき英語力や指導法について体験しましょう。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
社会科教育、教育方法、教師教育
主な授業:
初等社会科教育法、総合的な学習の時間の指導法
研究テーマ:
・持続可能な社会づくりのための授業開発
・幼保小連携、小中一貫教育のカリキュラム・マネジメント
幼保小連携や義務教育9年一貫したカリキュラム・マネジメントが求められています。子どもの学びや育ちを大切にしたカリキュラムをどのように構想・実現すればよいか考えましょう。
子どもの育ちには、グンと伸びる“当たり”があります。幼児の遊びのエピソードや小学生の作文などを手掛かりに、“当たり”をどう見つけ、関わり、ともに楽しむか考えてみましょう。
保育者や教師とはどんな仕事なのか。またその意義ややりがい、専門性はどのようなところにあるのか。保育者や教師という仕事に関心のある人たちとともに様々な面から考えます。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
保育学、幼児教育学
主な授業:
保育内容総論・保育者論・保育の方法と技術
研究テーマ:
・子育て支援
・保育実践
・保育者養成
園内研修は、日程の確保やどのようなテーマで行うかなど実施が難しいと考えていませんか。日常のちょっとした時間に保育の場面について皆で語りあってみませんか。明日の保育に生かせるような新たな気づきがあるかもしれません。
乳幼児期の子育ては特に親への負担がとても大きく、大変なものです。子育てに閉塞感や拘束観を感じていませんか。一人目の子どもの月齢が3ヵ月であるならば、親としての経験も3ヵ月です。“親になる”ということをテーマに乳幼児期の子どもとの向き合い方について考えてみましょう。
現在、数値で測ることのできない非認知能力に注目が集まっています。そしてこの非認知能力は特に乳幼児期の遊びを通して身に付くとされています。子どもたちの遊びの様子を通して、子どもたちの学びについて考えてみましょう。そして子どもたちの学びを支える保育という仕事のやりがいについてお話します。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
社会福祉学、児童福祉
主な授業:
社会福祉、子ども家庭福祉、社会的養護
研究テーマ:
・包括的子育て支援施策
・地域における子育て支援から社会的養護への接続
子育て支援、社会的養護において地域で子どもの育ちを保障する取り組みがさまざまな形で進められています。子どもの育ちを保障し、代弁者として役割を果たす専門職として、子どもの立場にたって家族や地域とどうかかわっていくのか、コミュニケーション技法など対人援助の基本から一緒に考えていきたいと思います。
少子化が進むなか子育て支援の必要性が指摘され、地域での相談支援窓口が整備されています。子育て支援には、子ども自らの育とうとする子育ちとそれを促して支える保護者などによる子育てがあります。妊娠期から児童期・思春期と子どもが育つ過程で生じる課題に対して、地域の中にどのような子育て支援があるのかお話しします。
少子化という言葉が一般的に使われるようになったのは、1990年の1.57ショックからといわれています。少子化は出生率が低下し、子どもの数が減少していることで、子どもや若者が少ない社会を少子社会と呼んでいます。そのような少子社会おいて子どもの育ちを保障する専門職として保育者が果たす役割について考えます。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。
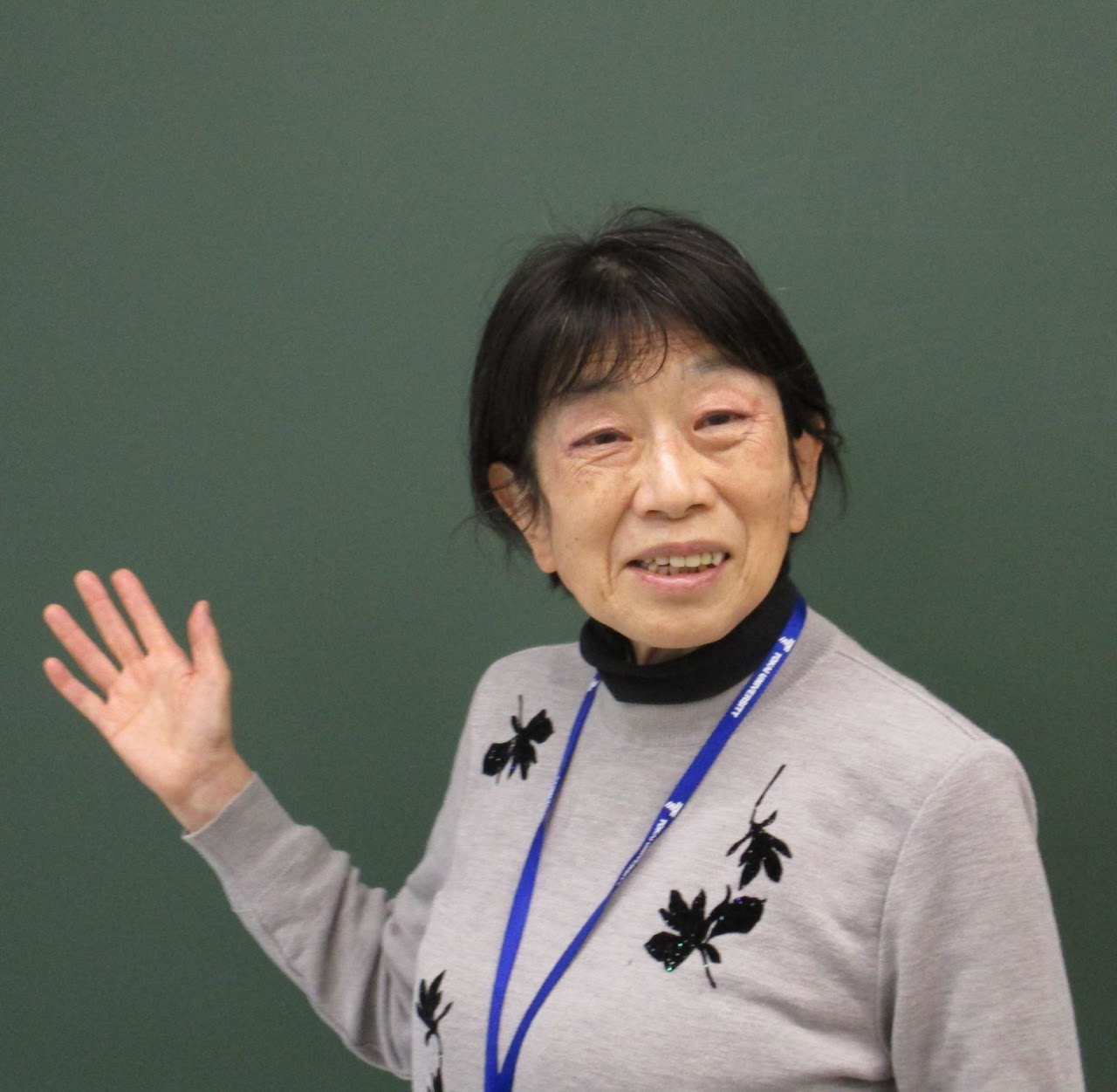
専門分野:
算数教育学、算数教育史
主な授業:
初等算数科教育法、初等算数
研究テーマ:
・大正期の算数教育
・総合的な学習
・問題解決学習
子どもたちの学びをみとり、どのように支援していくのかについて、具体的な例をもとにしてお話しします。算数の世界は不思議に満ちています。子どもたちがその世界を自由に探検できるように、子どもたちと一緒に歩く方法を考えていきたいと思います。
算数はとっても大切、でも実は苦手。そんな気持ちをお持ちの方も多いかもしれません。ところが少し見方を変えれば、楽しく面白い世界が開けてきます。保護者の皆様が算数の面白さを味わうことで、問題が解けずに悩んでいる子どもたちを、余裕をもって見守っていただけると嬉しいです。
算数を発見することや自由に使ってくことは、わくわくする経験です。自分ひとりでじっくり考えることも楽しいですが、友だちと一緒に議論すると思いがけない発見があって、もっと楽しくなります。そんな経験を子どもたちと一緒に作っていきたいと思います。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。
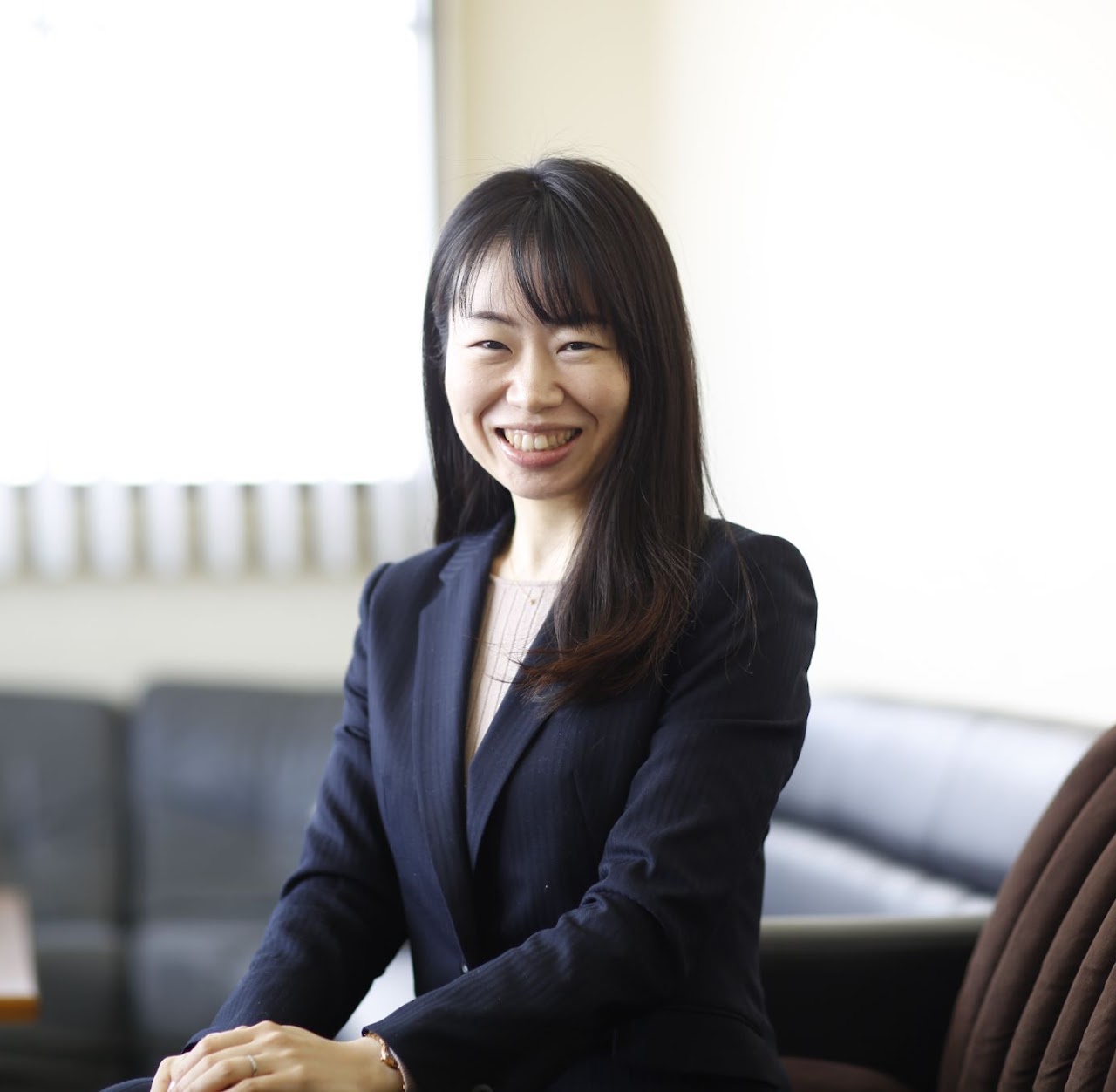
専門分野:
子ども学・環境教育
主な授業:
環境の指導法、幼児理解、実習指導(幼稚園)
研究テーマ:
・ドイツと日本の森の幼稚園
・持続可能な社会の構築と保育
・ホリスティック教育
自然と子どもをテーマに、持続可能性や自然体験の意味などについて、国際的な動向も踏まえながら解説します。併せて、SDGs(持続可能な開発目標)やESD(持続可能な開発のための教育)の取り組みについて、海外の事例なども紹介しながらお話しします。ワークなども取り入れながら、実践的に学びを深められるような講座を目指しています。
現代社会に生きる子どもたちにとって、自然との関わりはますます重要なものとなっています。本講座では、私たちの暮らす地球環境の現状や国際的な動向を解説しながら、乳幼児期の子どもの自然体験が持つ意味などについて、国内外のさまざまなデータに基づいてお話しします。
幼児教育や保育を学ぶ上で基本となる、「園生活における子どもの育ち」「保育者の役割」「子どもの遊びの意味」などについて、実際の子どもたちのエピソードなども交えながら、お伝えします。また、自然との関わりに着目して、日本とドイツの森の幼稚園の様子もご紹介します。「子どもの世界のおもしろさ」や「保育の深さ」を一緒に味わってみませんか。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
社会心理学、教育心理学
主な授業:
保育の心理学
研究テーマ:
・共感性が行動に与える影響
・共感疲労に影響を与える要因の検討
保育・教育現場において,教職員が組織における役割や連携の理解をすることは重要です。そこで,教職員の連携やチームワーク作りについての心理学の基礎理論を解説します。研究活動や社会貢献活動歴については,こちらをご参照ください
「子どもは何もできない未熟な存在なのか?」といった疑問について,心理学の基礎理論に基づき解説します。子どもの心の成長を支える周囲の大人の存在と関わり,親を支える存在の重要性についてもお話しします。研究活動や社会貢献活動歴については,こちらをご参照ください。
「子どもは何もできない未熟な存在なのか?」といった疑問について,心理学の基礎理論に基づき解説します。子どもの心の成長を支える周囲の大人の存在と関わり,親を支える存在の重要性についてもお話しします。研究活動や社会貢献活動歴については,こちらをご参照ください。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
児童・発達心理学、発達臨床心理学、学校心理学、カウンセリング、教育相談、生徒指導、教育心理学
主な授業:
教育相談(カウンセリング)、教育心理学、子育て支援の心理学
研究テーマ:
・学校での児童・生徒の支えあう関係づくり
・学校心理学に基づく学校予防教育と子どものレジリエンスの育成
・いじめのない学校づくり
・児童生徒のメンタルヘルス(心の健康)、学校適応
・子どもの安心と安全
・学校予防教育
・幼児・児童のセルフコントロール
・共生社会の実現
・子育て支援・虐待予防
近年、社会の変化が激しく、コロナ発生以降、予測のつかない状況が続いており、おとなでさえこうした状況に適応することが困難な時を過ごしています。こうした状況の中、自然災害も含め、だれもが事件・事故に遭遇し、被害を被る可能性はゼロではありません。私たちは普段から様ざまな経験を重ねる中で、大小様ざまな傷つきを経験しています。
こうした状況の中、子どもの安全を確保し、いかに安心して教師や仲間とかかわり、学校生活を送ることができるのかは今を生きる子どもたちにとって、また、子どもとかかわる保護者、教師にとって非常に重要なテーマです。これを実現するための取り組みとして、教師と子どものかかわり、子ども相互の関係づくり、クラス・学校全体(チ―ム学校)での取り組みなどについてお話しします。また、子どもの成長と発達を支える立場から、教師が子どもとのかかわりを通して、子どもの傷つきをいかに癒し、予防することができるのか、についてお話したいと思います。(特に、「学校ぐるみ」で「継続的に」こうしたことに取り組みたいと望んでおられる学校と連携して、子ども支援、学校支援を行うことを望んでいます。)
子どもにとって保護者は、子どもの命と成長を支える大事な存在です。親は子どもが生まれた途端に親としての役割が求められますが、親の方は、子どもとのかかわりを通して親として学び、成長していきます。保護者へのお話では、こうした考え方を基本として、子どもの成長と発達を理解し、子どもの成長を支える子どもとの関わり、子ども一人ひとりの個性の理解、個性を生かす関わり、親としての成長についてお話しさせていただきます。虐待予防の取り組み、保護者支援も行っています。
子どもたちはいろいろなことに追われ、忙しく、ストレスの多い日々を過ごしています。また学校生活の中で、教師・おとなとの関係、友だち関係に時に傷つき、そして疲れています。子どもたちは仲間とかかわる中で、人を傷つけたり、傷つけられることに非常に敏感です。
子どもたちには、様ざまな人とのかかわり、人とのかかわり方、互いに支えあう関係づくり、日々のストレスを解消するセルフマネジメント、などについてお話しさせていただきます。児童・生徒へのお話では、単に話を聞いてもらうだけでなく、実際に身体を動かして活動したり、仲間、先生との交流も含めて行い、子どもたちの仲間関係、教師と児童生徒との関係、学校生活の中での「学び」も変化することをめざしています。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
特別支援教育
主な授業:
特別支援教育・障がい児保育に関連する科目
研究テーマ:
・通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒に対する支援
障害の有無にかかわらず、授業中などに離席をする、大声や奇声を発する、集団活動に参加できないなど子どもは様々な問題行動を示すことがあります。問題行動は、一般的には厄介な行動、困った行動として捉えられがちですが、実は、「問題行動はコミュニケーションの一手段」なのです。そこにはちゃんと意味があります。この子どもが示す問題行動をどのように理解し、またどのように支援をしていけばよいかについてお話します。
子どもがゲームばかりしていて、なかなか宿題に取りかからない、子どもを褒めようと思っているがつい叱ってしまう、子どもが朝なかなか起きられないで、いつも遅刻しそうになる。子育てには悩みがつきものですが、子どもが示す行動をどのように理解し、またそれに対してどのように支援をすればよいかについて具体的にお話します。是非、あなたも子育て名人になってください。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
教師教育学、教師教育政策
主な授業:
教職論、教育制度論
研究テーマ:
・教員の資質向上
・教育政策の動向
・教師像
子どもをめぐる状況変化が多い中で、教育・保育現場はその対応に戸惑い、不安と困惑を感じることはないでしょうか。子どもたちに何が起きたのか、なぜ変化が起きたのか、現場はどう戸惑うか、望ましい問題解決の糸口は何なのか、教育問題の全体像についてお話しし、これからの教育・保育について考えます。
早期教育を幼児期の子どもに受けさせるかどうかという悩みを受けて、発達段階における大人の教育支援と人間形成の大切さについて、教育学の基礎理論に基づきお話しします。
これから教員・保育者を目指す高校生には、どうすれば先生になれるのか、どのような先生が子どもたちに好かれ信頼されるのかについてお話しします。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
学校教育学、カリキュラム学
主な授業:
教育課程論、学校教育論
研究テーマ:
・カリキュラムの社会学
・学校社会学
・学校教育学
教育課程のテーマが中心です。学習指導要領や年間指導計画として想起される教育課程について、「カリキュラム」(学習経験)という広い視点から捉えています。教育改革の重点も「教えから学びへ」と移りつつあります。カリキュラム・マネジメントによる授業改善はこの動向を示しています。日本の先生方が積み上げてきた教育成果をさらに質的に充実させるための試みをご一緒に考えてみましょう。
世界の学校教育は21世紀に入って大きく変化しています。私たちが経験した学校教育と今のそれはどこがどう違ってきているのでしょうか。そしてそれはなぜそう変わってきたのでしょうか。将来の社会を生き抜く子供たちにとって保護者はどんな学びを提供すればよいのでしょうか。問題を解くカギは生涯学習につながるカリキュラムの在り方にあります。世界の改革動向も参考にしながら考えてみましょう。
何のためにこんな内容を学ばなければならないのだろう?そんなことを考えたことがあるでしょう。「それを考える暇があったら勉強しなさい」と言われたことでしょう。学ぶ意味と生きる意味をつなげて考えることはカリキュラムの大事な研究テーマです。学ぶ主体には学ばない自由があるのでしょうか?学校での教えと学びのパラドックス(矛盾する状況)について考えてみましょう。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。
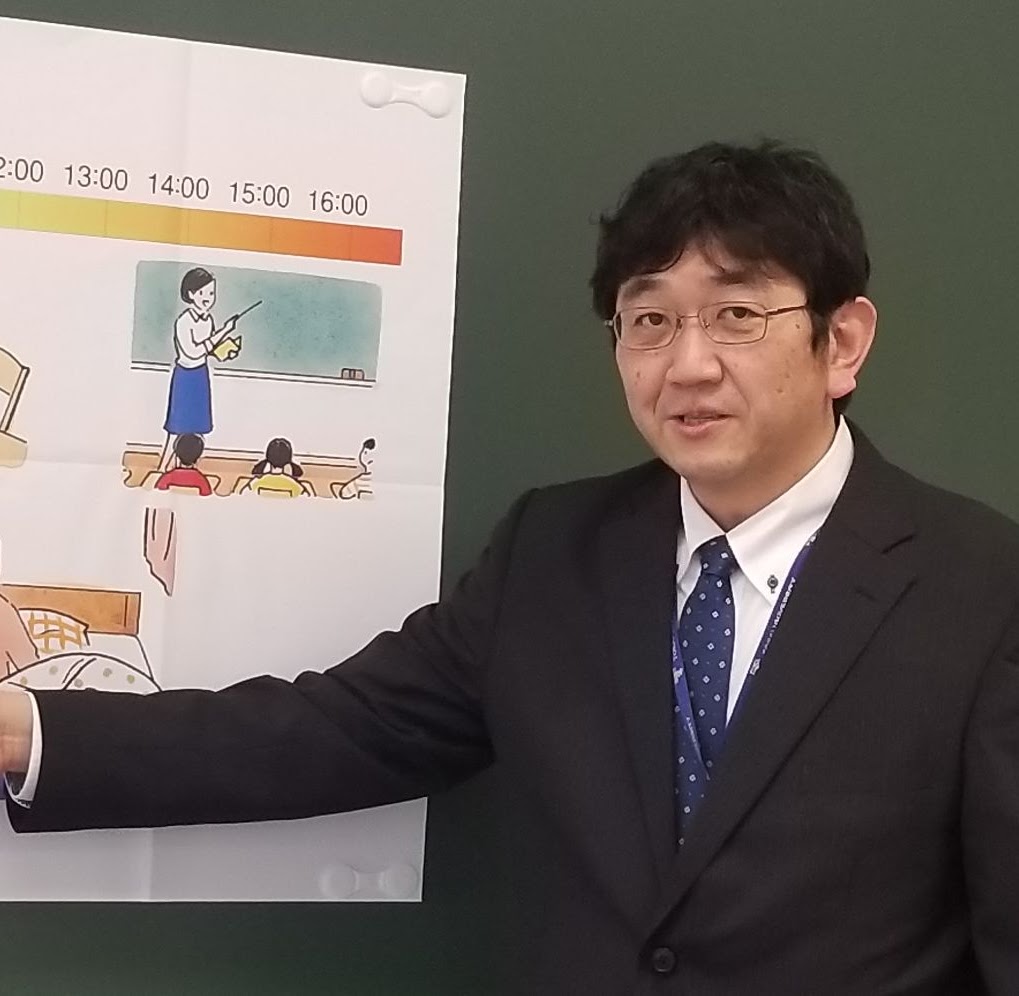
専門分野:
英語教育学
主な授業:
初等英語、初等英語科教育法
研究テーマ:
・小学校での英語教育
・異文化コミュニケーション
・英語一貫教育
小学校においては、中学年で「外国語活動」、高学年では「外国語」の授業が行われています。子どもに英語を学ばせる意義や、どのような授業を行えばよいのかを「コミュニケーション」という観点からお話しします。
小学校での英語の必修化に伴い、英語塾に通う児童や英語を取り入れる幼稚園・保育園・こども園が増えています。このような状況下で、子どもと英語との関わりはどうあるべきかについてお話しします。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
美術科教育
主な授業:
初等図画工作、表現(造形)、図画工作科教育法
研究テーマ:
・子どもの造形活動に関する質的研究
・美術鑑賞学習の指導と評価に関する研究
・日本近代の美術教育およびデザイン教育史
幼児の造形活動、小学校図画工作科、中学校美術科の表現や鑑賞について、指導改善に役立つ具体的なお話しをします。授業の各題材において、ねらいや評価、子どもたちの主体的な活動を促す表現や鑑賞学習の指導法について、演習を交えてお話しします。
幼児の遊びの意味や子どもの絵の発達や見方をはじめ、表現や創作を支える保護者の在り方や接し方についてお話をします。また、美術作品を実際に鑑賞してもらい、その楽しさを体験してもらいます。
各学校や園の指導計画に合わせた題材、図画工作科の教科書に掲載された表現や鑑賞題材について、先生方と相談しながら幼児や児童に直接授業やワークショップを行います。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
生活科教育、スタートカリキュラム、保幼小連携
主な授業:
初等生活、初等生活科教育法、接続期カリキュラム研究
研究テーマ:
・スタートカリキュラムと幼保小連携
・生活科を中核とした低学年教育
「子どもを育てる」園・学校から「子ども自らが育つ」園・学校へ、一人ひとりの子どもを主語にする保育・教育を目指したいと考えています。私たちが子どもを育てたつもりでも、子どもに身についていないことはなかったかという自戒の念が込められています。小学校入学当初で実施されている「新しいスタートカリキュラム」や保幼小連携について理解することで、一緒に考えていきましょう。
子どもにとって安心することはなんでしょう。それは、まわりにいる大人の笑顔、そして、共感のまなざしです。子どもは、安心しなければ自己を発揮できません。安心感が、子どもたちの意欲や主体性、学びに向かう力を引き出すことにつながります。それには、まず私たち大人が広い心、ゆったりした心で子どもたちと接することが大切です。「子どもは学ぶ意欲と学ぶ力をもった有能な学び手である」と言われています。どれだけ子どもの立場に立てるか、実際の子どもの姿から一緒に考えていきましょう。
「学びに向かう力」は、テストで測ることはできませんが、あきらめない心や粘り強さなど豊かに生きていく上で欠かせない学力です。非認知能力とも呼ばれています。「学びに向かう力」を育むには、「手応え感覚」が大切だと言われています。入学当初に実施されているスタートカリキュラムでの1年生の子どもの姿を通して、手応え感覚、そして、学びに向かう力について考えてみましょう。小学校教師としてのやりがいについてもお話します。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。
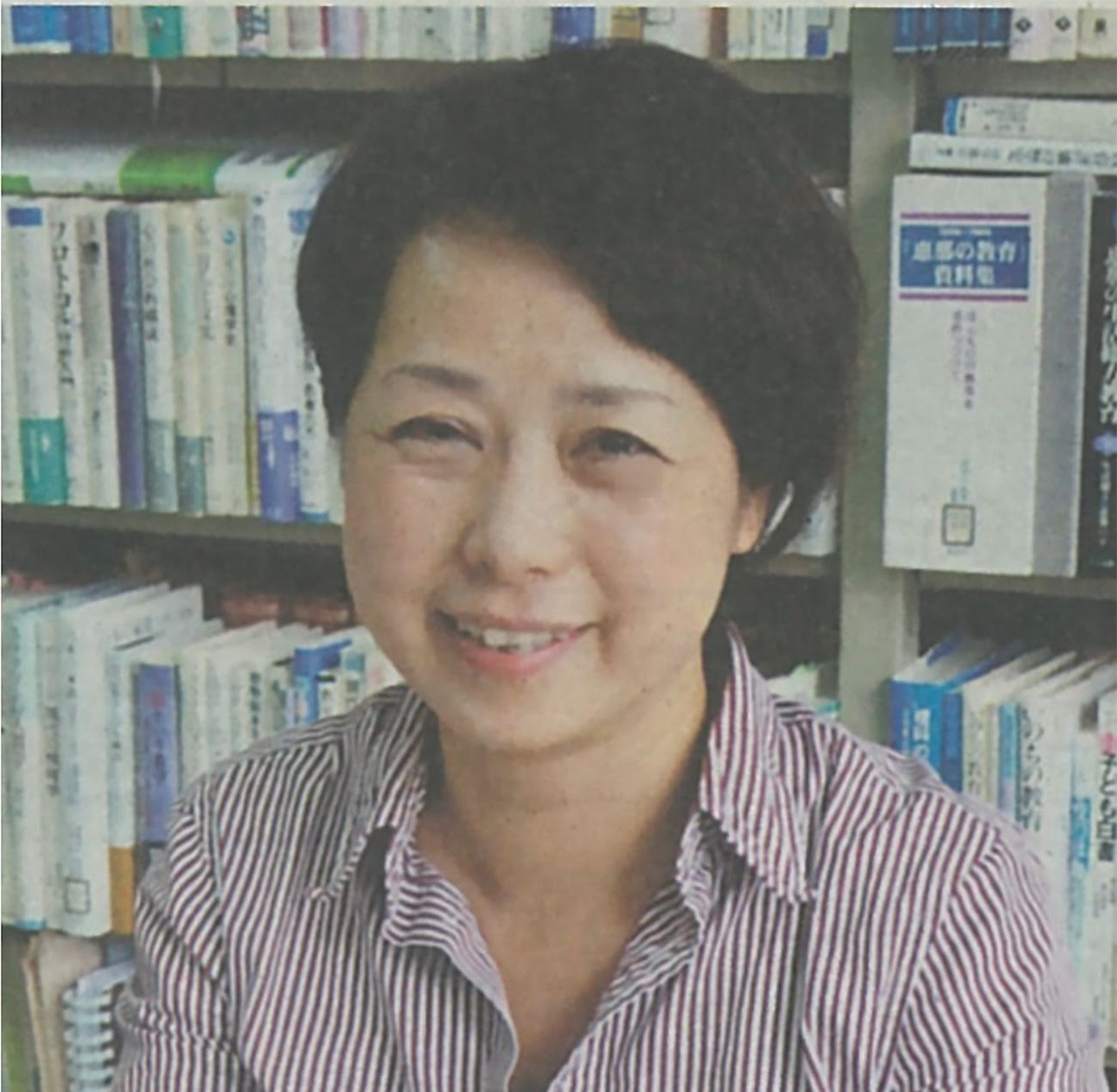
専門分野:
教育学、教育史
主な授業:
教育原理、幼児教育原理、保育の歴史
研究テーマ:
・子どもの生存保障の歴史
・地域の教育史
・教員の教育研究運動の歴史
現在、保育・教育の世界は大きく変わりつつあります。めまぐるしく変化する日常の中で、多様な価値観を認め合い、共同して子どもを育てることは容易ではなくなりました。また、フリースクールや子ども食堂などの民間セクターによる学習支援や家族支援の実態を踏まえ、地域と連携した保育・教育計画を立てることが重要となっています。チームとしての園や学校のあり方について考えていきます。また、学校記念史の作成等を教育史の観点から支援することができます。
子どもの育ちは、大人に見えている以上に複雑で、行きつ戻りつを繰り返しながらじょじょに進んでいきます。小学校高学年から始まる思春期を乗り切り、青年期の進路選択と向き合うには、豊かな幼児期・児童期の保障が必要です。ところが、子どもの貧困や虐待などが日本でも広がっており、子どもの生存自体が脅かされている実態が指摘されています。そこで「子どもの権利条約」などを紐解きながら、全ての子どもが安心して大人になることができる社会について考えたいと思います。
受験という人生の登竜門をくぐり抜けてきたみなさんは、今、さまざまなタイプの高校が登場しているのをご存じでしょうか。新しい分野のコース設置や、普通科と農業科と水産科が相互に交流する高校が登場したり、通信制高校の生徒数が2020年に初めて20万人を超えるという動向も注目されます。このような多様化の一方で、一部では受験競争が加熱化し、他方では退学を繰り返すケースも問題になっています。「いろいろ選べるけど不安」な高校の現状を知り、理想の高校教育について考えます。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
音楽教育学、声楽(主に日本歌曲)
主な授業:
初等音楽科教育法、表現(音楽)の指導法
研究テーマ:
・教員養成課程における音楽(科)教育の在り方について
・日本歌曲を中心とした声楽諸作品に関する演奏研究
・保育の専門コースを擁する高等学校に関する調査研究
保育内容「表現」について、主に音楽表現や劇表現(ドラマ表現)を中心としたワークショップを通して、保育者の皆さんとこれからの「表現活動」について考えていきます。
全国高等学校家庭科保育技術検定の実施校の先生方を対象に、日ごろの検定指導(主に音楽・リズム検定)や審査に関して、困難に感じていることを共有しながら、課題解決に向けたアドバイスを行います。
「主体的な音楽学習」をテーマに、情報機器等を活用した音楽鑑賞や歌唱の授業を行います。
「学校教育ではなぜ音楽を学ぶのか?」をテーマに、その歴史的背景や幼保小接続期における音楽(表現)活動の実際などの学習を通して、知見を深めます。また、全国高等学校家庭科保育技術検定の実施校の生徒を対象として、検定(主に音楽・リズム検定)合格に向けた理論や技術指導を行います。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

専門分野:
アダプテッド・スポーツ科学、特別支援教育
主な授業:
健康、健康の指導法、初等体育、アダプテッド・スポーツ など
研究テーマ:
・不器用な子どもの運動発達支援
・障害児・者の余暇活動支援
・特別支援教育
教育・保育現場の「気になる子」の理解と支援について、インクルーシブの視点から具体的なアプローチについて解説します。また、運動発達支援の立場から、特に身体的不器用さのある子の指導・支援について、実践的な学びにつながるよう実際のケースを交えながら講座を展開していきます。ニーズに応じて、アダプテッド・スポーツの実技講習も行います。
子どもたちの発育・発達は、乳幼児期から始まり、学齢期の学習へダイレクトにつながります。一方で、教育・保育現場の「気になる子」の多くに、様々な不器用さがみられます。本講座では、子どもの運動発達に着目し、乳幼児期から学齢期にかけて求められる不器用な子どもの運動遊びの方法や考え方について、家庭でも取り組める実践方法や実技講習を交えながらお話しをいたします。
本講座では、自分とは違う他者への理解を深めることをねらいとして、様々な運動やスポーツのニーズに対して、実際にアダプテッド・スポーツの体験をしていただきます。
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。
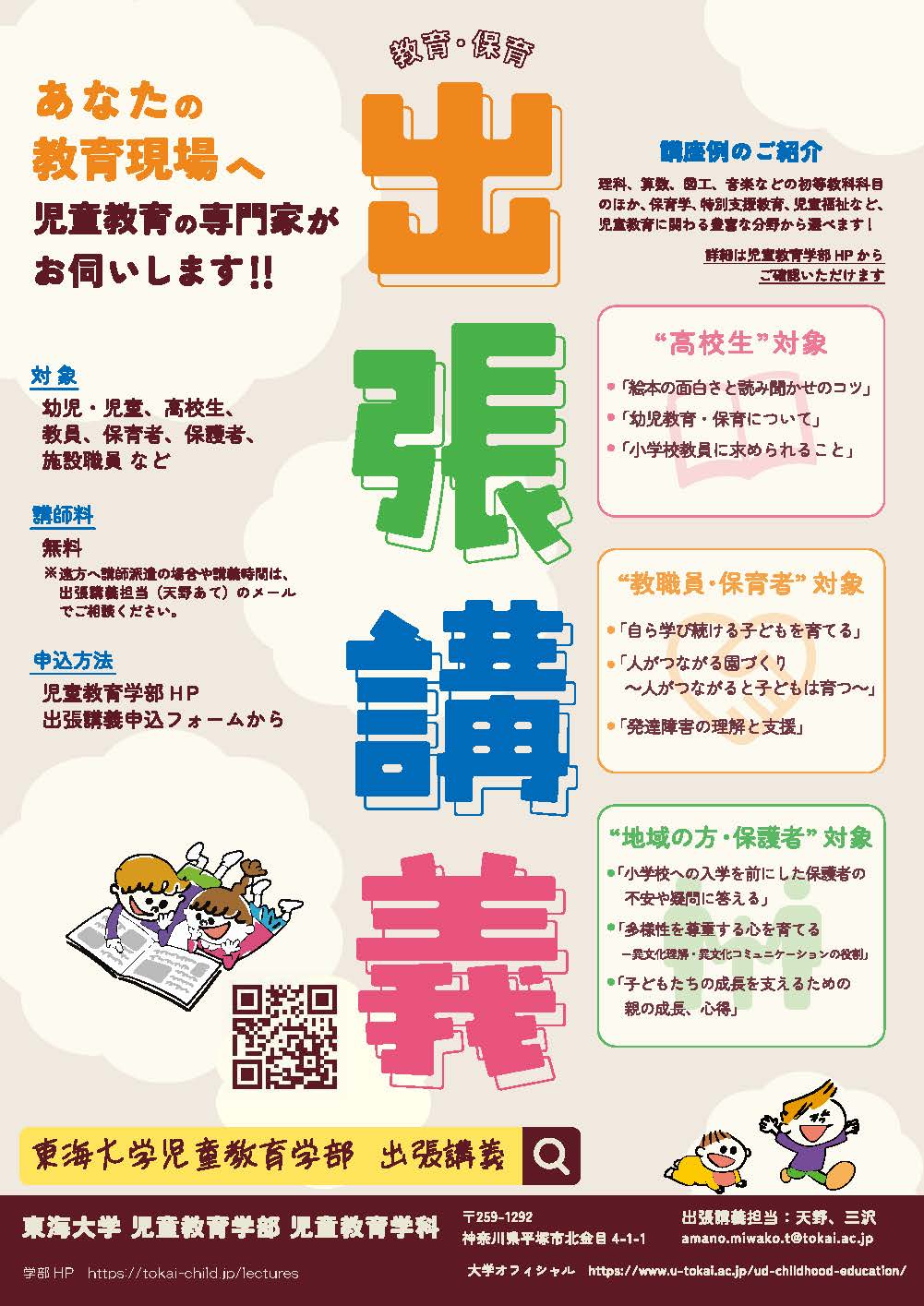
出張講義を希望される方は下記の申込みフォームからお申し込みください。下記画像をクリックするとリンクにジャンプします。
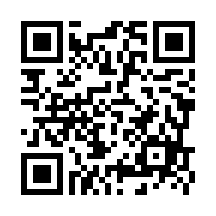
ご不明な点がありましたら,下記までお問い合わせください(「アットマーク」を記号に変えてください)。
amano.miwako.tアットマークtokai.ac.jp
〒259-1292
神奈川平塚市北金目4丁目1−1
東海大学児童教育学部